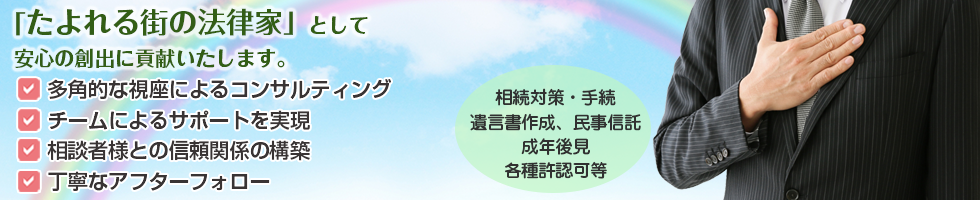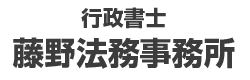「争続」を防ぎ、「想続」を実現するために

「相続」という言葉に触れたとき、最初に何をイメージされますか?
「うちはたいして資産があるわけでもないし関係ないだろう」「その時になってから考えれば良いだろう」「何らかの準備をしなければならないのかもしれないがきっかけがない」など、確かな裏付けのないままにその場をやりすごしてしまったり、いまひとつ前向きに考えることができず遠い将来のこととして無意識のうちに日常から遠ざけている人も多いのではないでしょうか。確かに相続は人の死によって発生する法的手続きであるため、年齢が若ければ若いほど、健康的な生活を送ることができている人ほど、日常生活を通じて自分の死後を積極的に考える契機は少なく、ともすれば縁起が悪いテーマであると避けてこられたのも当然のことかもしれません。
よって、これまでの時代には事業を経営している家庭や先祖代々受け継いできた資産を承継していかなければならない場合など、積極的に資産防衛をしなければならない事情を抱える場合を除いては、先立って相続に関する問題を検討することは非日常的なテーマでありました。
しかしながら、今や時代は変わりつつあり、「相続」というキーワードをもってテレビや新聞などのメディアで取り上げられることは度々で、書店に足を向ければ相続にまつわる書籍が数限りなく置かれるようになりました。
それだけ人々が注目していることの証左であり、人生の先々を考える際に避けては通れない重要なテーマであることが認識されるようになったのだと思います。